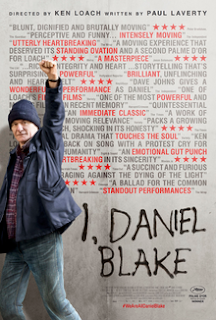オーストラリアで医療通訳とナーシングを25年間してきたが、腕にナチスドイツが押したプリズンナンバーが刺青されているホロコースト生き残りの人に、2回出会っている。子供の時に入れ墨されたのだろうが、年をとってもユダヤ人としてナチにキャンプで押された認識番号は、はっきり読み取ることができて、胸がつぶれる想いだった。
ホロコーストが人類に与えた影響は甚大で、この事実をもとにして沢山の小説や映画が制作され、今でも製作され続けている。
同じころ日本軍はアジア諸国で侵略を進め、中国、韓国、シンガポール、マレーシア、フィリピン、グアム、ニューギニア、ガダルカナルなど諸国を侵略し、他国民を蹂躙した。戦後日本軍の犯罪に対して、日本人以外の人々が描いた小説や映画は、ナチのホロコーストを描いたものに比べて極端に少ない。その原因に、未だ日本軍が行った残虐非道な行為がまだ充分掘り起こされておらず、一般認識されていないうえ、日本政府がその非をはっきり反省していないからだ。侵略を国土摂取による近代化と教育を授けただけと、開き直り、慰安婦を軍が関与していないとシラを切り、南京虐殺を無かったなどと言う。
ヨーロッパではホロコーストが無かったと発言することは、れっきとした犯罪で告発され、反社会的な人間として葬られるのに比べ、日本では南京虐殺が無かったと歴史を否定しても、犯罪と認識されないばかりでなく、国会議員にでもなれるという、恥知らずがまかり通っている。
最近、「沖縄護郷隊」という言葉を初めて知った。沖縄戦で、諜報機関として知られる陸軍中野学校出身者42人が沖縄に潜入し、沖縄護郷隊を作り、10代の少年約1000人が、米軍に向けたゲリラ戦を戦わせられた、という歴史的事実が知られることになった。米軍に包囲され投降する沖縄住民を後ろから銃で撃ち殺し、ガマに隠れた住民を追い立てて米軍の爆撃にさらした日本軍だ。地元が戦場となった沖縄の当事者にとって、日本軍のスパイとしてゲリラ戦を戦うなどという、余りに残酷な体験は、何年経っても声高に語ることができなかっただろう。それでも同じ歴史が繰り返されないために、語り出した歴史的証人の言葉に、私達は真摯に耳を傾けなければならないと思う。
歴史的事実を残っている写真やドキュメントで、くりかえし発表し続けることが重要だが、事実をもとにした小説や映画がもっと出ても良い。ナチスドイツに関する作品で、このブログで映画紹介と映画評を書いたものだけでも、「白バラの祈り」(ソフィーショール)マルク テムント監督、「否定と肯定」ミックジャクソン監督、「ヒットラーの偽札」ステファン ルオスキー監督、「戦火の馬」ステイーブン スピルバーグ監督、「優しい本泥棒」べレイン パーシバル監督、「ミケランジェロプロジェクト」ジョージ クルーニー監督、「ヒットーラーの忘れ物」マーチン サンフレット監督、「プライベートライアン」スチブン スピルバーグ監督、「サウルの息子」ラスロ ネメッシュ監督、「愛を読む人」ステファン ダルトレイ監督、「ソフィーの選択」アラン パクラ監督などがある。
一方日本軍に関する映画では、「アンブロークン」アンジェラ ジョリー監督、「軍艦島」リュ スンワン監督、「レイルウェイ マン」エリック ロマックス監督、「フラワーオブワー」チャン イーモー監督などがある。
 ナチスドイツが人間に、一体何をしたのか、日本軍がどのようにして権力を我が物にしてきたのか、それでどんな歴史的汚点を作って来たのかということを、どんなに語り、表現しても表現したりない。もっと、もっと反省を込めて反戦映画が出て来なければならないと思う。
ナチスドイツが人間に、一体何をしたのか、日本軍がどのようにして権力を我が物にしてきたのか、それでどんな歴史的汚点を作って来たのかということを、どんなに語り、表現しても表現したりない。もっと、もっと反省を込めて反戦映画が出て来なければならないと思う。
映画「サラの鍵」
フランス映画
監督:ジル パケ ブルネ
原作:タチアナ ド ロスネ
キャスト
ジュリア : クリステイン スコットトーマス
サラ : メリュジーヌ メヤンス
ヴェロドローム デイヴェール事件を扱った作品。(RAFLE DU VELODROME D'HIVER)
第2次世界大戦下、ナチスドイツ占領下にあったフランス、パリで1942年7月6日にユダヤ人が大量検挙された事件を言う。ヴィシー フランス政府はナチスの要求するまま、パリとパリ郊外で1万3152人(そのうち4115人は子供)のユダヤ人を警官が検挙した。ヴェロドローム デヴェールというのは、冬季競技場の名前で、検挙されたユダヤ人は、5日間ここに閉じ込められ、屋根のない真夏の競技場で、暑さと食糧、飲料を与えられないまま人々はその後 アウシュビッツなどの東欧各地の収容所に送られた。このような過酷な扱いに、ほとんどの人は生存できなかった。
第2次世界大戦下、ナチスドイツ占領下にあったフランス、パリで1942年7月6日にユダヤ人が大量検挙された事件を言う。ヴィシー フランス政府はナチスの要求するまま、パリとパリ郊外で1万3152人(そのうち4115人は子供)のユダヤ人を警官が検挙した。ヴェロドローム デヴェールというのは、冬季競技場の名前で、検挙されたユダヤ人は、5日間ここに閉じ込められ、屋根のない真夏の競技場で、暑さと食糧、飲料を与えられないまま人々はその後 アウシュビッツなどの東欧各地の収容所に送られた。このような過酷な扱いに、ほとんどの人は生存できなかった。
映画のなかでも、警察に引き立てられた人々が、「どうしてこんなひどいことをするの?私はフランス人よ。あなたも同じフランス人なのに。」とパリ警察に抗議するシーンが出てくる。当時ヨーロッパでユダヤ人が憎まれていたとはいえ、自分たちが自国の警察官によって検挙されてホロコーストに会うなどと、夢にも思っていなかった当時の市民の姿が垣間見られる。この映画は、10歳のサラが、深夜パリ警察に連行されるシーンから始まる。
ストーリーは
1942年7月6日。
深夜、パリ警察が乱暴にドアをたたき、父親の居所を問い正す。10歳のサラは、とっさの機転で、警察は、父親と弟の男だけを連行するのかと思い、弟を子供部屋の戸棚の中に隠し外から鍵をかける。たとえ自分が連行されても取り調べだけで、すぐに家に帰れると思っていた。弟には、どんなことがあってもサラが迎えに来るまで戸棚から出てはいけない、としっかり言い聞かせた。サラと母親は外に出され、別棟に隠れていた父親と共に引き立てられた。両親とサラはジープに乗せられ、競技場に連行され、コンクリートの上で炎天下何日も留め置かれた。その間、弟のことを案じた家族は警官に、弟を見つけて連れてくるように頼み込むが、誰も聴く耳を持たない。サラは熱中症で倒れ、家族はバラバラにされて列車に乗せられ、収容所に向かった。そしてそのまま二度とサラは両親に会うことがなかった。
3日3晩高熱で苦しんだのちサラは意識を取り戻す。弟のことが気になって一時もじっとしていられないサラは、収容所の警備員に鍵を見せて必死で弟を連れてきたいと懇願する。一人の警備員が10歳の子の尋常ではない頼み方に心が傾き、収容所の鉄条網をゆるめてやる。サラは走りに走ってパリをめざす。人家をみつけて家畜小屋で眠っているところを百姓夫婦に助けられる。夫婦には息子が居たが戦場に送られていた。夫婦は、サラを不憫に思い、警察に隠れて危険を承知で自分の娘として育てる。サラのたっての願いで、夫婦はサラを連れて占領下のパリに出かける。もとサラが住んでいたアパートに着いて、サラの持っていた鍵で開けた戸棚には、、、。
2002年ヴェロドロームデヴィエール60年周年記念の5月。
新聞社に勤めるジュリアは、この事件について論評を書くように依頼される。彼女はアメリカ人だが、フランス人の夫との間に14歳の娘がいる。新たに妊娠していることがわかった。家族はパリに居を構えることになり、夫の遠い親戚からパリのアパートを貰い受けたので、改築する予定だ。アパートの寝室には古い大きな戸棚がある。
論評を書くにあたってジュリアは、その古いアパートに戦争時に住んでいたスタルズスキ一家について調べることにする。そこに住んでいたユダヤ人家族は戦時中どんな生活をしていたのか。やがてジュリアは、この家族には2人の子供が居たはずなのに、収容所で死亡した両親の記録があっても、子供達の死亡記録がないことに気がつく。夫の遠い親戚たちや公文書から、家族にいたはずのサラと言う名の子供の足跡をたどる。そしてサラが養父母に大切に育てられ、アメリカに渡り、家庭を持ったことまで調べ上げる。
サラはホロコーストを生き延びてアメリカに渡っていた。ジュリアはその足跡を追って、アメリカに飛ぶ。サラの夫は老体で死の床にいた。サラはその夫との間に息子をもうけていた。息子は幼いうちに母親を亡くしたので、サラのついての記憶がない。
ジュリアはサラの人生を追うことによって、自分の人生がサラの人生の重さに重なって、もうサラを知る前の自分に戻ることが出来なくなっていた。というお話。
才覚ある10歳の娘が最愛の弟を守ろうとして、逆に死なせてしまう。その十字架を背負ったまま戦後まで生き残ったサラが家庭を持ち、息子を育てることになるが、息子が死んだ弟の年に近付くに連れて、原罪意識から逃れられなくなっていく。
哀しい哀しい物語だ。
ホロコーストで殺された600万人の人には、600万のサラのような悲劇的な物語を抱えて死んでいったのだろう。
サラの息子は、かたくなに自分の過去に口を閉ざして、そのまま何も語ることなく亡くなった母親が、ユダヤ人だったことも、ホロコーストの生き残りだったことも知らずに成人していた。彼は母親が残した形見の宝石箱に残された鍵の意味を知らずに、ただそれを思い出として大切に持っていた。
サラの生涯を調べつくしたジュリアは、サラの人生に深くかかわるに連れ、自分が妊娠中であるにも関わらず夫と理解し合うことができなくなり別れて 一人で娘を産む。
ジュリアがサラについてのすべての物語を息子に語り聞かせたあと、息子はふと、ジュリアの赤ちゃんは何という名なの、と尋ねる。何という名前?ジュリアはしばらくためらったあと、サラという名なの。と答える。それを聞いて泣き崩れる息子とジュリアのシーンで映画が終わる。とても心に残るシーンだ。
戦争の激しい暴力にさらされて、奇跡のように生き残った生存者が、戦後しばらくして自ら命を絶った、その胸の内が哀しい。「ソフィーの選択」も同様に戦後を生き続けることができなかった男女のお話だ。人は生き延びさえすれば良いのではない。失ったものが大きすぎる。耐えられるものではない。人はそんなに強い心をもって生まれてくるわけではない。
とても哀しい良質な反戦映画だ。